深々と頭を下げられたので、アリスは慌てて首を横に振った。
「そんな、お礼だなんて。当然のことをしたまでですから・・・」
「ですが・・・」
と、これまたランサムの時のように、ホテルの主人から顔色を窺われたウル。
「なんだよー?おっさん。人の顔ジロジロ見て」
「い、いえ・・・。その・・・『清く美しい関係』は大丈夫なのかと・・・。ああっ、すみません、余計な事を・・・」
その言葉にアリスの方がハッとして、途端にオロオロし始めた。
あのランサムという人が本当に気の毒に思い、思わず部屋を譲ってしまったのだが、自分の身の危険まで考えなかった。
今更になって、自分は大胆な事をしてしまったのだと気付いた。
そんなアリスとホテルマンの信用ならない雰囲気にウルは口を曲げ、フンと鼻を鳴らした。
「けっ、なに?お二人さんのその疑いの目。そんなの、俺がガマンすればいーだけのことだろ」
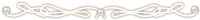
「かーーーッ!足が棒ーーーッ!」
ウルは部屋に入るなり、担いでいた荷物を床に放り投げ、ソファに腰掛けた。
その後ろから俯き加減に入ってきたアリスの目に入ってきたのは、ベッドだった。
「・・・」
一つしかない。
シングル部屋なのだから、当然なのだけど・・・。
「どうしたの?アリスも座って休めば?」
「え!?あ、ん・・・」
「そのベッドはアリスが使いなよ。あとでおっさんが簡易ベッド用意してくれるっつってたから、俺そっちで寝るし」
「ううん。ウルが使って。私がランサムさんに部屋を譲ってしまったんだもの。それに簡易ベッドじゃウル、ベッドから落ちてしまうわ」
痩せているワリには身体が大きいし、アリスが今まで見てきた彼の寝相はいつも子供のように大の字になってかなりの面積を使っている。
強いて言うなら、『思いっきり寝てる』という言葉が相応しい。
常設してあるベッドでさえ、彼にとっては小さいのではないだろうか?
「大丈夫、大丈夫。落ちてもたぶん、気付かないまま寝てるだろうから、俺」
そう言ってアリスの手から荷物を奪い取り、ベッドの上に置いてやった。
「ありがと・・・」
「いいって、いいって」
手をひらひらさせ、にっと笑う。
でもアリスは笑い返す余裕もなくて、所在無くその場に立ち尽くしていた。
そんな凍り付いている彼女を、ウルは不思議そうに窺う。
「・・・?ホント、どうしたの?アリス」
その声でやっと、アリスは一歩が踏み出せた。本当にやっと。
テーブルのそばに寄って、あらかじめ用意してあったティーセットに手を伸ばした。
「・・・あ、えっと。わ、私、お茶淹れるね。喉かわいたでしょ?」
なんだか、ウルのそばにいる事がためらわれた。
今はこうして彼に背を向けて逃れる事で、どうにか普通にしていられる。
(普通・・・?)
アリスは心の中で首を傾げた。
今の自分は、全然普通ではない。
(ものすごく不自然よ、私・・・!)
ウルは今までずっと、そばにいてくれた人。
それはとても自然な事だったけど、こうして改めて壁に囲まれた空間に二人きりでいると不思議なもので、とんでもなくウルを意識してしまう。
ウルに勘付かれないよう平常心を心掛けつつ、ティーカップに紅茶を注ぎいれていると、背後に気配を感じた。
顔だけ振り向くと、ウルが真後ろに立っていた。
「アリス・・・」
「ウ、ウル・・・!?」
驚きで体がびくっとした拍子に、ティーカップとティーポットの注ぎ口が、ガチッと合わさる陶器の音が響いた。
「・・・」
「・・・」
その野性味を帯びた鋭利な瞳に見つめられ、体が金縛りにあったかのように動かない。
肉食獣が、獲物を捕まえようとする時の緊迫感が張り詰めた空気。
ふと、彼と出会ったばかりの頃、人食いの村で『このお姉ちゃんを食べちゃうのは、俺様なんだよーっ!!』とウルが叫んでいたのを思い出した。
あの時は呆れてしまったが、今はどうなんだろう?私の気持ち。
・・・やっぱり、少し怖い。
でも。怖いけど、ウルとなら私・・・――――。
「ねえねえ。どうなってんの?」
「・・・え!?」
どうなってんの――――・・・って?
アリスは、おっかなびっくりの表情でウルを見た。
彼は先程の『今すぐ、取って喰ってやる』という視線が消え失せ、眉間に皺を寄せて難しそうな顔をしている。
どちらかというと、好奇心に満ちた子供の目。
「な、なに?なんのこと?」
「前々から不思議に思ってたんだけど、その頭って、こう、クルクルってウニウニって感じで、難しそうな髪型だよね?」
 「か、髪型・・・?」 「か、髪型・・・?」
「ウンウンそうそう。いっつも、ひっつめ頭じゃん?アリスちゃんて」
「ひっつめ・・・頭・・・」
ウルが背後で腕を組みながら、後頭部をしげしげと物珍しそうに観察してくるので、思わずアリスは頭を両手で抑えた。
「すっげえ手が込んでない?律儀にも、いっつも同じ髪型だもんな」
「い、いーでしょ別に」
「あッ!!」
「なによっ、大声出してっ」
「もしかしてさ、ヅラ!?」
「ヅ・・・!?」
アリスは絶句して、キッとウルを睨んだ。
「そっ、そっ、そんなわけないでしょーーーッ!!」
拳を上げて怒り出したアリスから飛び退く。
「ハハッ、冗談だって。ジョーダンっ」
「うう〜っ、もうっ!」
ウルが腹を抱えて笑っているので、アリスは悔しくて唇を噛んだ。
ひととおり笑い終えたウルは、ひーひー言って苦しそうだ。
涙を浮かべて笑っていた。
「なによお。そんなに笑う事ないでしょ!!」
「おーっと、おっかねー。んじゃ、アリスちゃんのご機嫌が直るまで、ちょっくら出掛けてくるかな」
「ええっ?出掛けるの?今から?」
「ウン」
「だって・・・今日はもう遅いし、疲れたから、お祭りは明日出掛けようって、さっき話したのに」
置いてきぼりされると思っているアリスに、ウルは首を横に振った。
「祭りはアリスと一緒に行くって、明日。さっき、フロントのおっさんがさ、このホテルの隣りにバーがあるって言ってたから、ちょっとそこで一杯ひっかけてこようかなと」
「・・・ふうん」
「じゃっ、いってきまーす」
と、軽く手を挙げ、ドアノブに手をかけたウルだが、一瞬そこで立ち止まり、そのまま後ろ歩きしながらアリスの所へと戻ってきた。
「?」
「あー、あのさ。帰り遅いかもしんないから、さき休んでてよ。あ、それと鍵締めといていいよ。俺、鍵持ってくから」
|
 「か、髪型・・・?」
「か、髪型・・・?」