
ここ数日のことを思い出してみたら、疲れることばかりが身の上に降りかかったように思えてならない。
いろいろありすぎた。本当に。どうしようもなく。
月影族のみが出入りする、レイラン城の地下奥にある執務室。そこでイルシアはそのどうしようもなくいろいろあったことを独り、書面に記しているところだった。
「はあ…」
溜め息もつきたくなる。
楽しい旅行になるはずが命を狙われ、予断を許さない旅となってしまった。満喫できなかったばかりか、帰って来てみればその事件の報告書作成だ。
事件に関わったのがナーグスという指名手配中の男だったため、上層部に報告しなければならなくなり、せっかくの休暇を返上してまでこうして仕事をする破目になってしまったのだ。
しかも、シムとルーカに押し付けられて。
「…」
押し付けられたときのことを思い出したら、余計に面倒くさくなってきた。
ペンを放り投げ、椅子の背もたれに身体を預ける。
「友達甲斐のない奴らめ。手伝うって気持ちがないのか?」
文句も言いたくなる。
確かに今回の事件は、イルシア自身が狙われたことによるものであるため、報告書の作成は致し方がない。
しかし、最初に襲われたのはあの二人で、そのことについての詳細を知りたいのにシムとルーカからは「適当に書いといて」と、適当にあしらわれた。彼らは明日まで休暇を取っていたらしく、とどのつまり、ただそれを返上してまで仕事をしたくないのだ。
「くっそー。本当に適当に書いてやる」
再びペンを手に取り、なぶり書く。
だが突然、重要な事に気がついた。
『シムとルーカの部屋にイルシアが居るとナーグスが勘違いし、彼らの部屋に襲撃に来た』などと報告したら、必然的にイルシアとマリエが同室だったということになる。
(…長老やエラマ様にばれるだろ…これ)
ここはひとつ脚色しなければならない。しかも嘘だとばれないように問題なく、だ。
どうやって?
「…」
ますます仕事がはかどらない。ペースが落ちてきた。
机に顔を伏して、結局またペンを放り投げる。
なんで俺だけが、こんなに考えて悩まなくちゃいけないんだよ…。
今回はマジで疲れただけだった……。
「あっ、いたいたー!」
唐突なその明るい声に嫌な予感がして、イルシアは亡霊の如くゆっくりと振り向く。
そこにはルーカが立っていた。
「…なんだよ」
「なんなのよ、その間は。しかも私が登場するたび、どうしてそういう根暗な顔するわけ」
「別に。っていうか、ルーカが休暇返上してまで城に来たってことが気味悪いんだけど」
「失礼ね。その言い方、すごく失礼しちゃう。すごくいいこと、言いに来たのにさ」
またかよ…。
イルシアは頭を抱えた。
「あんたの『いいこと』は、俺にとっては特にそうでもないんだよな」
「可愛くないヤツね」
ゲンコツが頭上に飛んできて、更にイルシアは頭を抱えた。
「いてえ…」
「あんたが投げたボールが長老の頭に当たって、私が身代わりになって謝りに行ってやったことがあるのに!」
「いつの話だ」
二十年以上も前のことだ。恩着せがましいにもほどがある。
しかもその借りはとっくの昔に返してある。確か見返りにと、隣町までお菓子を買いに行かされた。
「とにかく!イルシアが不憫だからって今晩、シムと私で夕飯おごってあげるって言いに来たんだからね」
「それならそうと早く言えって」
「あ、ちなみにマリエちゃんも招待したよ」
またかよ…。
今回の旅行でこりごりしたので、シムとルーカが一緒の時はマリエを伴いたくない。だが、ルーカはそれを絶対に許さないだろう。そんな不満顔のイルシアに気付いて、彼女は仁王立ちしたまま睨んでくる。
怖い。
「いい?イルシアの恋人である前に、マリエちゃんは私の友達なの。誘っても別に私の勝手でしょ」
「友達ぃ?」
「なに。悪いっての?」
「だって、あいつ魔物使いだし…」
それは、この世では間違いなく畏怖の対象なのだ。好き好んで友達なんかになりたいと思うのかどうか疑問だ。
「そういうイルシアだって、恋人じゃないの」
「それはそうだけど…」
確かに最近、ルーカと買い物に出かけたり食事に行ったりしているということはマリエから聞いてはいたが、イルシアとしては『エラマ様の娘』ということで、マリエに気を遣ってのことだと思っていた。
だがルーカは、本当に友達だと思ってくれているようだった。
「ほら、マリエちゃんて、私たち一族にはいない人格じゃない?新鮮なのよね〜、一緒に遊んでも楽しいし。あのほんわかした雰囲気がなごむし」
月影族だけでなく、世界中捜してもあんな女はいないと思ったが、それよりもマリエを友として接してくれる者が現れたことを喜ばしく思った。
「まあ、お言葉に甘えて今晩おごってもらうとするよ。いつもの店に行けばいいんだな?」
「うん」
「それまでに報告書、仕上げるよ」
頑張って、と声をかけてからルーカは部屋を出ていこうとしたが、踵を返す。
「そういえば言い忘れてた」
「?」
小脇に抱えていた書類らしきものを目の前にちらつかせてきたので、イルシアはルーカを睨みつけた。
「まさか、また『癒しの旅程表』とか言うんじゃないだろうな」
「あはは。まさか。たとえそうだとしても、昨日今日ですぐに日程組めないよ」
今回の旅行の帰り道、馬車の中でシムが、「今度は湖か川に泳ぎに行こう!」と血気盛んに提案していたのだ。疑いたくもなる。
「ちゃんと見なさい。ほら」
「報告書?」
しかも作成者は、イルシアの昔の恋敵及び天敵とも言えるハズリンクだ。
「さっき、温泉旅行の顛末を長老に簡単に口頭で報告したらね、これ貸してくれたの」
イルシアはそれを手に取った。
厚く綴られている書類を一枚ずつ目を通していくうち、眉間に皺が寄っていく。
「なんだよ、これ…」
「びっくりでしょ?」
びっくりどころか、開いた口が塞がらない。
内容はこうだ。
ハズリンクは任務として、消息不明となった月影族の調査をしていた。その彼が、その一人であるナーグスの居場所を突き止めたというのだ。ナーグス本人と接触、話し合いをし連行しようとしたが、取り逃がしたとある。
しかもその話の中身は、イルシアがナーグスから聞いた同じ内容が書かれており、ナックの名前はもちろんアサエル・シーズとイルシアの名前も列挙されていた。
ナックは一般民として暮らしていたこと。自分はいまだアサエルの命令のままに行動していること。そしてその命に従い、イルシアを抹殺すること―――
「いつの報告書だよ」
このことを事前に知っていれば、無闇に温泉旅行なんて気楽な計画を実行しなかったのに。マリエを巻き込むことだってなかった。
作成日を確認したら、イルシア達の温泉旅行1日目の日付になっている。
「実際にナーグスと接触したのは、私たちの旅行前日のようよ。場所はイムグ街になってる。ヒーリノ温泉の近くね。ハズリンクはナーグスを取り逃がしてすぐ、早馬で王都に戻ってきたらしいんだけど、ちょうど私たちと入れ違いだったみたい」
間に合うわけがない、か。
「だから俺に、ナーグスのことを伝えられなかった…」
「長老の話じゃ、温泉旅行から帰って来てからこのことを伝えるつもりだったらしいわよ。イルシアを殺すためにまっすぐ王都へ向かうかと思われていたナーグスが、まさか温泉街へ寄るとは思ってもみなかったらしくて」
「その忠告を聞く前に、俺が自分からナーグスの懐に転がりこんじまったってワケだ」
俺の運が悪かったとしか言い様がない…のか?
「どうせなら、ナーグスを改心させて欲しかったって、俺の意見としてそこに書き加えたいよ…」
投げやり気味に吐き捨てて、ぶっきらぼうに書類をルーカへ返した。
「ハズリンクだって努力したみたいじゃない?この報告書を見る限りではさ、ナーグスにイルシアを殺すなって説得したみたいだし。大急ぎで王都に戻ってきたのだって、あなたの身を案じてのことでしょう?」
あのハズリンクが…?と疑いたくなるが、確かに個人的な感情で動くような男ではない。いくらイルシアを毛嫌いしていたとしても、知らん顔をするわけがないのだ。
個人的に気を遣ってくれた可能性は低いと思うので、ただ月影族の一員である者を助けるというあくまで仕事の一環だと考えているに違いないと思えば、納得もいく。
「まぁ、俺だって別にハズリンクに文句を言いたいわけじゃないよ。結局、ナーグスのやつは巫女さんの言葉にだって耳を傾けようとはしなかったし。それだけあいつにかかっている『アサエルの呪い』は強力だったってことだ」
「でも、マリエちゃんはナーグスを改心させたんじゃないかな。『イルシア抹殺』は諦めないって言ってたけど、単なる捨て台詞でしょアレ」
「…だといいけど」
とは言え、実はイルシアもルーカと同じ考えだった。
ナーグスの性格からして、イルシアの息の根を止めるまであの場で決着をつけたに違いないのだ。だが、マリエの登場で闘争心が失せた。
「俺は巫女さんを守っていたつもりだったけど、結果的には、実は俺が巫女さんに助けられたってことかな」
無血で終わったのだから。
「そうよ。感謝なさい。それにマリエちゃんはナーグスも助けたんだから」
「ナーグスも?」
イルシアは首を傾げた。この仕草はマリエの専売特許だ。やばい、俺にまで伝染しつつある。
「アサエルのためなら時間なんて惜しくないって、これまた捨て台詞を吐いてたよね。でもきっと、これからはそんなことも無くなるでしょ。自分のために時間を使うんじゃない?大事にね」
「なんでそんなこと言えるよ?」
「だってさ、時間には逆らえないってナーグスも実感したと思う。ナックやハズリンク、そしてイルシアとマリエちゃん達に出会って、みんなそれぞれどこかしら変化していたことに気付いてる。変わっていなかった…ううん、変われずにいたのは彼自身だけだった。未来はやってくるってマリエちゃんに言われたことで、余計にそれを実感したはずよ」
そうかもしれない。
ナーグスだけは、イルシアとマリエが出会ったばかりの頃のままで時間が止まっているようだった。
何も変わっていなかった。ナーグスのやつだけは。
それにしても。
「…俺、変わったか?」
時々、自分でもそう思ったりもするが、他人に言われるとどんなふうに変わったのかが気になる。
ルーカはけらけら笑った。
「変わったわよぉ。マリエちゃんをすごく毛嫌いしてたのに、今じゃ、べったりのラブラブじゃないの」
「そういう変化かよ…。っていうか、勝手にありもしないこと言うな」
べったりってなんだよ、と言いたい。少なくとも、ルーカの前でそんなことをした覚えはない。
「やあね、照れちゃって、この子は」
茶化されると腹が立つ。睨んでやるとルーカはひらりと身をひるがえしながら、「じゃあね〜。また今晩ね」と、投げキッスを残して部屋を出ていってしまった。
「くっそー…、今回はこんなんばっかだったな…」
今回、というか、ここ最近ずっとだ。いいようにからかわれてばかりいる。
自分たちが変化したように、シムとルーカの茶化しも時間の経過とともに無くなっていくのだろうかと考えたが、はっきり言ってそれは愚問だとすぐに悟った。
あいつらが改心するわけがない…。
…まあ、いいか。
イルシアは、苦笑した。
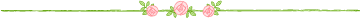
陽が落ちる寸前になんとか報告書を仕上げることができ、イルシアは急いでキュロイ神殿へ向かった。
既にマリエは勤めが終わっていたらしく、参拝者がくぐる正門の前で立って待っていた。
「待ったか?」
「はい」
即答、ときた。
「…あのさ、俺から助言」
「はい?」
「そういう時は待ったとしても、『そんなに待ちませんでした』とかなんとか言うんだよ」
「どうしてですの?」
「どうしてって…ちょっといじらしいとかって、思うんだよ。男ってのは」
「だって、本当に待ったのですもの」
「…可愛くない…」
こうやって迎合しようとしないところは、やはりマリエらしさとでもいうのか。決して変わることのない彼女の一部だ。ルーカはマリエも変わったと言っていたが…。
―――変わったか?
隣を歩く彼女を盗み見てみる。
瞬きのたびにまつげが踊っている様に魅入り、そして色白の肌に桜色の頬。思わず触れたくなるような柔らかな唇…
―――って、俺の見方が変わっただけじゃねーか!
イルシアはひとり狼狽する。
けれどマリエはやはり変わったのかもしれない。髪が少し伸びて、顔つきも以前に比べれば大人っぽくなったような気がする。とはいえ、まだまだ中身は子供っぽいか。
「なにかわたくしの顔に付いてます?」
「え」
「先程から、イルシアさんの熱い視線を感じますけど…」
「…。いや、なんでもない」
この狼狽をなんとか誤魔化したくて、咄嗟にハズリンクからの報告書について教えてやった。
彼女はその話題に興味を持ったらしく、真剣なまなざしで聞いているのでとりあえず安堵する。
「きっと、ハズリンクさんはイルシアさんのために、大急ぎで王都に戻ってきてくれたんですのね」
「俺のため…ねえ」
それはルーカにも言われた。ハズリンクは、ただ仕事の一環として王都に戻ってきたのだと解釈していたイルシアとしては、マリエにまでそう言われると、もしかしたら本当に自分のために…と思わずにはいられなくなるから不思議だ。
(俺だって前ほどハズリンクを嫌わなくなってるんだから、あいつだって俺に対して温和になってもおかしくはない話だな)
イルシアの昔の恋人であるレビイと結ばれたハズリンク。
彼らを祝福できる今、確かに自分は変わったのだと実感できる。
「なんかさ。自分じゃ変わったつもりはなくても、よくよく考えると知らないうちに変化してるんだな、人間て。こういうの、成長って言うのかな」
こくん、とマリエは頷く。
「だから、変わることは素敵なことですわ。ですが、変わらない普遍なものもありますけれど」
「変わらないもの、か」
たとえばそのマリエらしさ、だろうな。俺としては若干直して欲しい所もあるが…。
そんなイルシアの思いとは裏腹に、マリエはその相変わらずの笑顔で「たとえば、わたくしへのイルシアさんの愛情とか」と、図々しいことを言い出してきた。
ここでそんなことはない、と言い返せば恐ろしい魔物の逆襲が待ち受けているのは目に見えるため、イルシアは黙した。しかし余計にマリエの不審を煽らせただけだった。
「…どうして、そこで押し黙るのですか?」
「黙秘」
「むぅ。イルシアさんのいじわる!」
「うわ」
腕を振り回して追いかけてくるので、イルシアは逃げ出した。
「待って下さいっ」
「やだ」
走りながら―――しかし、マリエがちゃんと追いつく速さで走りながら。
振り向くと、彼女の背後に見える夕陽が眩しかった。
街並みにゆっくりと沈んでいくあの夕陽のように、普遍的で変わらないものは世界にたくさんある。たとえばこうして、マリエと些細な喧嘩をすること。これは昔から変わっていない気がする。
まあ、これは日常茶飯事ってやつか。
そのなんでもない日常というのが、このうえなく幸せで大切なことなのかもしれない、とイルシアは思う。
こうして二人でいられるという、なんでもないことが。
マリエがやっとのことでイルシアの腕をつかまえる。息を切らして。
「とうとう、つかまえました〜…」
イルシアがその手を取って、そっと手をつないできたのでマリエは少し驚いた表情をした。そしてすぐ、恥じらい気に彼を見上げた。
「イルシアさん?」
「さ、メシ食いに行こう。『俺達の悪友』が首を長くして待ってる」
瞬間、きょとんとしていたマリエだったが、すぐににっこりした。
「はい!『わたくしたちのお友達』ですわね!」
イルシアもつられて笑った。
きっと、これからたくさんの時間が流れて、いろいろなものが変化していく。
シム達の変わらない友情とともに。
目の前の彼女といっしょに。
「イルシアさんの手、あったかいです」
「うん」
少し遠慮気味にすり寄ってきた彼女のあたたかさで、心がオレンジ色の残像が映る夜空へと導かれた。
きれいだった。空も、マリエも。
ふと、一番星を見つけた。
イルシアは、その瞬く光にそっと願う。
―――ささやかなこの幸せが変わらずに、明日も続きますように。
おわり
≫next あとがき。。。
|