この旅が
ずっと続くといいのに・・・
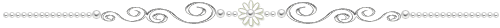
同じ夢を何度も見る。
眠っている時に見る『夢』。
それが未来を夢見る『夢』だとしたら、どんなにいいだろうって何度も思った。
その夢は最初、何も存在しない真っ白な空間で、少ししてからずうっと向こうに黒い小さな点が現れる。
そしてゆっくりとこちらへ近付いてくるそれは、次第に人影だということが分かってくる。
私にはそれが誰だか分かっているから、その人が近付いてくるのを心待ちにして、じっとその場で立ち尽くしている。
「アリス」
私を呼ぶ、懐かしい声。
現実の世界ではもう決して聞けない、優しい声。
それになんて温かい体温。懐かしい匂い。
そっと抱き締められて私は幸せな気持ちになるけれど、これは夢だって分かっているから少し悲しくて寂しい。
・・・・・・本当は私、ずうっとここにいたかったのに。
今この瞬間が、いつか未来に起こり得る事だったらどんなに幸せだろう。
でもそれは決して叶わない夢。絶対に。
だってこの人は、もうこの世にいないから。
私を助けるために、死んでしまったから・・・。
「お父様」
声をかけると、私を抱き締めていたお父様は目を細めて、にこりと笑ってくれた。
子供の頃から変わらない笑顔。
二人きりで旅をして辛いことがあっても、お父様はその笑顔で励ましてくれたから私は頑張れた。いつでも。
そして、その背中をずっと追いかけてきた。
でも、もうそれはできない。私は独り残されてしまったから。この世に。
・・・・・・お父様は、そんな私をずっと心配してくれているのね。夢にまで現れて・・・。
「アリス。ひとりぼっちにさせて、すまない・・・」
私は、ううん、と首を小さく横に振る。
「お父様のせいじゃないもの。謝らないで」
「しかし・・・」
「だってお父様は、命をかけて私を守ってくれました。お父様の力で安全な場所に逃げられたから、私はこうして生きることができたんです」
「アリス・・・」
それでも「すまない」と繰り返すお父様の瞳に、涙が滲んでいた。そして呟く。
「お母さんも私も志半ばでこの世を去ってしまい、お前だけをこんな荒ぶれた時代に独り残して・・・私は心配で心配で仕方ないんだ」
「そんなに心配しないで。もう子供じゃないんですから、私。二十歳の大人ですもの、大丈夫。それにね、ひとりぼっちなんかじゃないの。お父様とお別れしてからいろんな人に・・・本当にいろんな人に出会ったのよ」
「いろんな人?」
「仲間・・・っていうのかしら。皆さん、とても良くしてくれます。一風変わった人達ばかりですけど。陰陽道のおじさまとか、スパイを生業にしているお姉さまとか、吸血鬼さんとか。ええと・・・それに、まだいるんですよ」
心なしか、その残りの仲間の事を話すのが恥ずかしく思えた。
お父様にはぜひ聞いて欲しいような、でも隠しておきたいような・・・。
「まだ他にも仲間がいるのかい?」
「え・・・あ、ええ。あのね・・・その人、心の中にモンスターを棲まわせているの。そして、彼らの魂と自らの肉体を融合する力を持っているんです」
「・・・そんなすごい力を・・・」
「あ、でもね、いい人なの!私を助けてくれたし。見かけの雰囲気は怖そうだけど、本当は優しい人で・・・それに実は繊細だったりして・・・ええと、そう!名前はね、ウルっていう人」
「そうか」
お父様はまた、にこりと微笑んでくれた。
けれどすぐに眉根を下げて、悲しそうな表情に変わった。
「お前を支えてくれる大勢の仲間がいるのだから、心配は無用なのかもしれない。けれど、私の心配は消え失せない。たぶんアリス、おまえ自身がまだ心の内に、孤独という寂しさを抱えているからだよ」
「私の心が?・・・仲間がいるのに?」
お父様は深く頷いた。
「アリス。お前はどうして寂しいんだ?なぜ悲しむ?何を恐れている?仲間がいるというのに、なぜ孤独を感じる?」
「・・・」
「だから。だから私は心配でしょうがないんだよ、お前の事が。アリス、お前はひとりぼっちの悲しみをまだ持っているから・・・」
そしてもう一度、お父様は優しく包んでくれた。
温かく感じていた体温が段々冷たくなると、お別れの時間だということを悟る。
けれど私はその腕の中でじっとしている。お父様の姿が薄れ、無に帰っていくまでずっと。
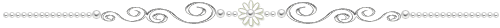
カーテンを開けると太陽はすっかり顔を出していて、まぶしいその陽光が薄暗かった部屋を一気に明るくした。
優しくて少し悲しい夢を見た後は、この太陽の光によって完全に現実に戻る事ができるのだ。いつも。
「また・・・お父様の夢・・・」
しばらくベッドの上でぼーっとしていたが、やっと頭の中が冴えてくると、こんなのんびりしている暇などない事に気付く。
「いけない!寝すぎちゃった!」
慌てて身支度を済ませ、階下のレストランへ行くと、隅のテーブルで既に朝食をとっている見知った男女を見つけた。
そのうちの女の方がこちらに気付き、小さく手を振ってきた。
彼女は遠めで見てもかなりのグラマーだし、仕草も座る姿勢もなんだか艶めかしいのでかなり目立つ。あれで本当にスパイなのかしら、と思う時が多々あるが正真正銘のスパイらしい。
「はぁ、はぁ・・・おっ、おはようございますっ、マルガリータさん・・・はぁはぁ」
「慌てて階段、下りてきたみたいね?ホテルのボーイに叱られなかった?」
くっくっくっ、と笑う姿も妖艶な感じ。
「でも、珍しいわね。アリスが寝坊するなんて。いつもは一番乗りで朝食を食べているのに。今日は大雨降るわね、きっと。私達の方があなたより早起きしちゃったんだから」
アリスは飾り柱にかけてある時計を見た。今、10時40分。
テーブルの上の料理にまだあまり手をつけていないところを見ると、マルガリータ達も今しがたここへ来たのだろう。
決して早起きしたと言えないのでは・・・
「うん絶対、雨か嵐ね、今日。ねえ、そう思わない?ウル」
マルガリータは向かいに座っているウルに同意を求めたが、彼が突然、ゴンッという派手な音と共にテーブルの上に頭を突っ伏したので驚く。
「なっ、なに!?急にっ」
「・・・寝てる・・・みたいですね」
アリスはマルガリータの隣りに腰掛けながら、テーブルに額をぶつけても眠っているウルを見て苦笑した。
「ッたく、食べながら寝るんじゃないわよっ」
マルガリータが足でウルの膝を蹴飛ばしたが、いっこうに目覚めない。
「そっとしておきましょう。疲れているんですよ」
「甘い!甘いわよ、アリス。こいつ昨夜、久し振りに繁華街に来たからって、夜中まで街中うろついてたんだからっ」
「そ、そうだったんですか・・・」
「そうよ。このだだっ広いロンドンで人探ししなきゃいけないのに、坊やがこんな調子じゃあ、先が思いやられるわホント」
コーヒーを一息に飲み干し、カップをソーサーの上に荒っぽく置いたら、その音に反応してか、ウルの体がピクリと動いた。
マルガリータはそれを見て、はぁ・・・と呆れながら頬杖をつき、寝癖頭のウルの髪の毛をニ、三本引っこ抜いてやった。
が、それでも起きない強靭の眠り。
|