
・・・しあわせ。
十九年間生きてきて、これまでにさほど不幸だなんて思ったことはない。
魔界の扉を開く為の生け贄だとかで、制限ある生活を強いられていたけれど。
人間の友達も恋人もいなくて、いつもいつも魔物達と遊んでいたけれど。
それでも、しあわせだった。
きっと他の人が聞けば、それは不幸だと言うかもしれない。
だが、マリエにとってはそうでもない。
本人がそう言い張るのだから、間違いはない。
しあわせのあり方など、人それぞれ違うものだ。
しかし、過去のことをあれこれ詮索しても仕方がない。大事なのは今だ。
現在の彼女の〝しあわせ度〟はどうなのかと聞けば、即答で返ってくるにちがいない。
「この上なく、しあわせですわ」
以前よりもっともっと。もっともっと。
だって、大好きなイルシアがそばにいてくれるから。
いろいろ遠回りしたりしたけれど、望んで望まれて手に入れた彼の愛情は、この世界で一番大切なものだと思う。
そしてかけがえのない、たったひとりの人。
イルシアだけの自分。
自分だけのイルシア。
そんな言葉が思い浮かぶ。
しかし―――。
こんな浮かれ気分のマリエにも、実は多少なりとも不安があった。
それはイルシアとの今後の付き合い方についてである。
マリエは恋愛についてまったくの初心者であるためか、『恋人』というイメージがいまいちピンとこないのだ。
イルシアとは単なる『友達』という関係から一転して、『恋人』になったことで、お互いの気持ちは通じ合っていると分かったが、他は特に変化があったわけでもない。
はっきり言って『なんとなく恋人』という言葉が、一番しっくりくる。
彼への振る舞いも今までどおりだし、会話もボケとつっこみで相変わらずだ。
そんなまったくと言っていいほど中身の変わらぬ関係なので、余計に『友達』と『恋人』の境目が見つけられないでいる。
何をどうすればよいのか、右も左も分からない。誰かに相談してみようかしら、などと思ったりもしたが、禁じられた恋ゆえにそれもままならない。
だが元来、悩みもあまりなく、重症と言えるほどの楽天家のマリエであるから、最近この事について考えるのは諦めたのだった。
いくら考えても分からないものは分からない。それでいいと思っている。
とにもかくにも今は―――。
「わたくしは、イルシアさんがいるだけでしあわせです」
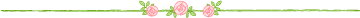
近頃、イルシアとマリエは毎日、会っていた。
相変わらずマリエは后候補の身だ。他の男とデートしているなどと知られればスキャンダルになるため、外をおおっぴらに出歩かないようにしている。
幸い彼女は、次期宰相と噂されている父・エラマと違い、人々にあまり顔は知られていないので、そんな神経質になることもないのかもしれない。
それでも、娘の恋愛を快く思っていないだろうエラマに、二人の関係を知られないためにも、やはり無闇に外出はしないほうが得策だろう。
いつどこで誰が見ているか分からないのだし。
こういう複雑な事情で、彼らの逢瀬はいつもイルシアの家だった。
彼は一人暮らしで気兼ねがいらない。それに、酒場などがある娯楽界隈に建っているため、夕方から朝まで人でごった返しており、それに紛れてしまえば、誰にも詮索されないだろうという利点がある。
いい気分で酔っていたり遊んでいたりと、他人の事など気にせずに、皆それぞれに楽しんでいるのだから。
そして今日もまた、その都合の良い彼の家で二人は過ごしていた。
「ね、イルシアさん。今日はどの章を読みましょうか?」
「・・・もしかしてまた、オーディダの教え?」
横に寄り添って座っているマリエに訊ねた。
彼女は分厚い経典をペラペラめくりながら、「はい!」と元気に返事をしてくれた。
「・・・」
イルシアは些か渋面になった。
それもその筈、貴重なせっかくの二人の時間なのに、経典朗読である。
しかも三日連続。
あまりにもつまらなさすぎる、辛すぎる、身が持たない・・・の苦痛3連発だ。
信者でもないイルシアにとっては、特に。
(聖職者をカノジョに持つと、デートはいつもこんなんなのか!?)
頭を抱えてみるが、元はと言えば読みもしないその本を、自分の部屋に置いておいたのがまずかった。
マリエを部屋に招き入れた三日前、イルシアさえ忘れていた本棚にあったそれを彼女が見つけてしまったのだ。
何年か前に、悪友シムから貰った物だった。
シムは、オーディダ教の総代司祭・スカリイと行き来があり、その所以で本をスカリイから数冊頂戴したらしいのだ。それでそのうちの一冊がイルシアに回ってきたというわけなのだが、特に興味もなかったので、ページをめくることもなく今に至ってしまった。
そして本棚の飾りと化していたのである。
「あのさ。なんかもっと、他の話にしないか?」
面白くなさそうにイルシアは、板張りの床に敷いてある絨毯に寝そべった。
「他の話ですか?」
「うんそう。楽しい話」
う~ん・・・と悩むマリエ。
何の話題を提供してくるかはマリエに任せて、自分はその彼女の横顔をこっそり見つめる事にした。はっきり言って本当は、どんな話題でも構わないのだ。
彼女がそばにいてくれればいい。イルシアはそう思っていた。
(ただでさえ、会っている時間が短いんだし・・・)
お互いの仕事が終わってから会っているのだが、エラマやチャウラに怪しまれないように夕飯前には彼女は帰っていってしまう。
少しでも好きな人と一緒にいたい。それが恋人同士だと思うのだが、「一緒にいたい」とさりげなく口にできないのは、まだお互いが初々しいのか、それとも素直じゃないのだろうか。
(まあ、雰囲気っていうのもあるよな・・・巫女さんはこういう人だから、色気のある雰囲気作りはなかなか難しいもんなぁ)
う~んう~んと、いまだ首をひねっている彼女を見ながら、溜め息を吐いた。
そんなイルシアの苦悩も知らず、やっとのことで話題を思いついたマリエが微笑みを投げてきた。
どうやら楽しい話題を思いついたらしい。
「じゃ、女神ルーナの教えの事でも話しましょうか!」
イルシアはすかさず飛び起き、「だからなっ、やめようって!そーゆーのッ!」と抗議した。
彼のその不満が理解できなくて、マリエは首を傾げている。
「変なイルシアさん」
「どっちが。変なのは巫女さんの方だろーが」
再び寝転がるイルシアに、マリエはむっとする。
「ひどい。そういうこと言うと、わたくし帰っちゃいますから」
「あっ、そう」
「むっ・・・。ホ、ホントに帰っちゃいますよ。引き止めてくれないとっ」
冷たい言い草に、よりいっそう頬を膨らまして文句を言ってやったら突然、イルシアに腕を掴まれ引っ張られた。
「!?」
あまりもの素早さだったので、イルシアの体の上に折り重なるように引き寄せられたマリエは、ただただ目を点にしていた。
してやったりと不敵な笑みを浮かべ、「引き止めるよ。当然」と悪ガキじみた口調で呟くイルシア。その彼に、「来たばっかりだろ」と言いながら抱き締められた時は、もっともっと驚いた。
でもふと、「こういうのが『恋人』って言うのかしら」と思った。
『友達』とは違う、『恋人』の特権みたいなもの。
お互いの存在を確かめ合うための甘い時間。
そう言えば近頃、イルシアはやけに髪や手などに触れてくる。だがマリエは彼の事が好きだから、別にイヤじゃない。むしろ嬉しいとさえ思っていた。
現に今、マリエはぽやーっとしていて、拒む様子もない。
「イルシアさん・・・」
その力強さに体が押し潰されるんじゃないかと一瞬不安になったけれど、彼がこんなに近くにいて触れ合っていると、なんだか安心した。
本当に。とっても。
でも・・・――――。
(・・・あれ?『でも』?『でも』って・・・何かしら?)
何か否定的なものを感じ、マリエは心の中で訝しがる。
イルシアのことが大好き。触れられてもイヤじゃない。
それなのに、何かが心に引っ掛かっている・・・。
|